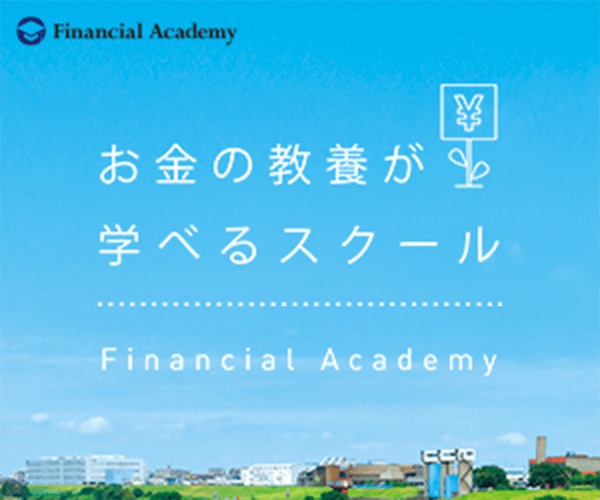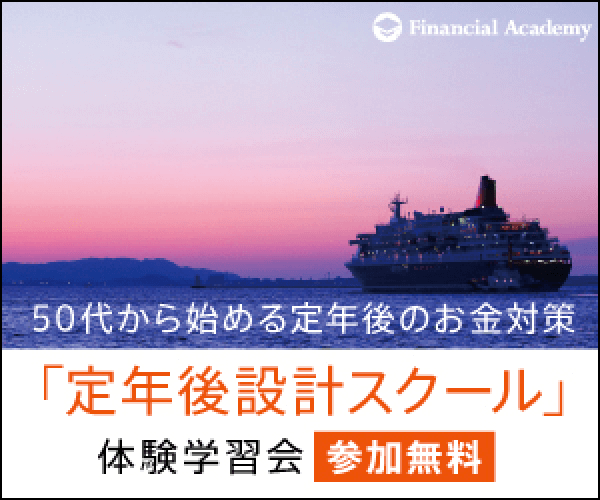こんにちは、億持ってない億男です。
物価の高騰が続き、日々の生活に負担を感じる人が増えています。「少しでも手取りを増やしたい」「税金が重く感じるようになった」そんな声がSNSや街の声で聞かれるようになりました。実際、社会保険料や各種税金の負担が上がる傾向にあるなか、「独身税」という言葉が注目を集めています。
この「独身税」、正式な税制ではありません。しかし、SNSなどで広まったこの言葉が、多くの人の関心を集めているのには理由があります。今回はこの“独身税”と呼ばれているものの正体について、わかりやすく解説していきます。
独身税は子育て支援のための税金
独身税というのは俗称であり、正式な名称ではありません。独身税と呼ばれている制度は、2026年4月から始まる「子ども・子育て支援金」のことです。
この税金は社会保険料に上乗せされるため社会保険に加入しているすべての人が支払うことになります。こども家庭庁によると、令和8年度では平均250円程度で、徐々に上がっていく予定だそうです。
子育て支援のため・・・ではありますが、物価が高騰している今の時代にわずかでも増税されると言われるとついつい敏感になってしまう方も少なくありません。
参考資料:子ども・子育て支援金制度について(https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkin)
独身だけが支払うわけではない
SNSで「独身税」と呼称されているため「独身者にだけ新たな税金が課される」といった誤解が生じやすいのですがこの税金は独身者だけが支払うものではありません。実際には子育て中の人や子育てが終わった世代、子供がいない既婚者など、すべての被保険者が支払うことになります。
ただし、子育て支援金によって恩恵を受けるのは、基本的に子どもがいる家庭と将来的に子供を持つことになる人に限られるため、「子どもがいない独身者は恩恵がない」「子育てが終わった人にはメリットがない」という見方があるわけです。
子育て支援で分断が生じている?
独身税や子育て支援が原因で、分断が生じているといわれることがあります。
子供を育てるということはとてもすばらしいことです。そして、当然のことですが、独身で子どもを持たないという選択も個人の意思として尊重されるべきです。どちらかがより優れているというものではないわけで、多様性は尊重されるべきなのが今の世の中のスタンダードです。
ですが、やはり分断や不満がないわけではありません。子供がいない人は子育て支援の恩恵は感じられないでしょうし、すでに子育てが終わった人からしても「自分のときには支援はなかったのに」という不公平感が生まれてしまうわけです。このように、制度の恩恵を直接的に受ける機会がほとんどないにもかかわらず、負担は同じように課せられるということでモヤモヤ感が残ってしまうのです。
一方で、SNSなどで「子供がいない人は、私達の子供から年金をもらうからメリットがある」という意見や「子育てしてないんだから税金くらい払って」という過激な意見も見られます。もちろんこうした過激な言葉はごく一部の人のものではあると思いますが、「独身税だ」と言われることで、子供の有無によって分断が生じやすくなっているという側面もあります。
このような立場の違いはあれど、それぞれがなんとなく持ってしまう「モヤモヤ」が「これって実質的に“独身税”では?」という声につながっているのでしょう。
子育て支援制度の税金は増えていく?
子育て支援制度のための税期は令和8年度では平均250円ですが、それ以降値上げされる予定です。少子化という社会問題にいわば「お金を使った支援」をして対策をしているわけです。
確かに日本の少子化は深刻で、出生率はどんどん下がっています。人が少なくなるということは、国力の低下にも繋がりかねないため対策は必要です。
ですが、そのような中でも個人の意思や選択は尊重されるべきというのも事実であり、少子化対策は決して簡単なものではないというのも実情です。
少子化対策のためという大義があれど、増税は増税・・・。わずかな金額でもその分所得が減ってしまうのは事実です。
まとめ
「独身税」という言葉は、正式な名称ではなく、子育て支援のために導入される「子ども・子育て支援金」の俗称です。実際には、独身かどうかに関わらずすべての人が広く負担する制度であり、それによって少子化対策をしようというものです。
しかし、子どもを持たない人やすでに子育てが終わった人は、制度の恩恵を感じにくく、「自分ばかりが負担している」と感じるのもまた現実。そのため、「独身税」という呼び方が広まり議論を呼んでいるのです。ですが、独身だから税金を払いなさい!という趣旨ではないことだけはしっかりと認識しておきましょう。
このような制度を考える際には、ただ「誰が負担するか」だけでなく、「社会として何を目指すのか」「公平性をどう確保するか」といった視点がとても重要です。これからの税制・保険制度をどうするべきか、社会全体での議論が必要なタイミングなのかもしれません。